2012年03月01日
お勉強
昨日、閉校式に帰省した娘を送ってちょっとお勉強しました
熊本駅、西口~東口通路に展示してあります。
≪おきん人形≫
湯女のおきん女という美人薄命の娘を悼んで作られた人形で、別名≪弁太人形≫といいます。
200年も昔から日奈久で作り続けられています。こけしみたいです

≪おばけの金太≫
加藤清正が熊本城を築城の折に「おどけの金太」と呼ばれる人気者がいたそうです。
その言い伝えから、からくり人形はつくられたとか。
首のところの紐を引くと、真っ赤な顔の金太さんが舌を出しながら、目玉をぐるりとまわして、人々をビックリさせます
だから、いつしか≪おばけの金太≫と呼ばれるようになったそうです。
熊本では≪目くり出し人形≫とも言われています。
≪木葉猿≫
型を使わず指先だけで粘土をひねって作り、素焼きの荒いタッチの素朴さと、とぼけた味の玩具でもとは無彩ですが、彩色したものもあります。三匹猿・子抱猿・飯食猿など10種類位あり、悪病・災難除け、子孫繁栄などのお守りとして用いられています。
養老7年の元旦に「虎の歯(このは)」の里に住んでいた都の落人が、夢枕に立った老翁のお告げによって奈良の春日大明神を祀り、木葉山の赤土で祭器をつくり、残った土を捨てたところ、それが猿に化けたという伝説から生まれたものと伝えられています。

そして、伝統工芸品の横には今の≪くまモン≫が多数いました。
≪くまモン≫は、やっぱり可愛い
いっぱいお勉強した1日でした\(~o~)/


熊本駅、西口~東口通路に展示してあります。
≪おきん人形≫
湯女のおきん女という美人薄命の娘を悼んで作られた人形で、別名≪弁太人形≫といいます。
200年も昔から日奈久で作り続けられています。こけしみたいです


≪おばけの金太≫
加藤清正が熊本城を築城の折に「おどけの金太」と呼ばれる人気者がいたそうです。
その言い伝えから、からくり人形はつくられたとか。
首のところの紐を引くと、真っ赤な顔の金太さんが舌を出しながら、目玉をぐるりとまわして、人々をビックリさせます

だから、いつしか≪おばけの金太≫と呼ばれるようになったそうです。
熊本では≪目くり出し人形≫とも言われています。
≪木葉猿≫
型を使わず指先だけで粘土をひねって作り、素焼きの荒いタッチの素朴さと、とぼけた味の玩具でもとは無彩ですが、彩色したものもあります。三匹猿・子抱猿・飯食猿など10種類位あり、悪病・災難除け、子孫繁栄などのお守りとして用いられています。
養老7年の元旦に「虎の歯(このは)」の里に住んでいた都の落人が、夢枕に立った老翁のお告げによって奈良の春日大明神を祀り、木葉山の赤土で祭器をつくり、残った土を捨てたところ、それが猿に化けたという伝説から生まれたものと伝えられています。

そして、伝統工芸品の横には今の≪くまモン≫が多数いました。

≪くまモン≫は、やっぱり可愛い

いっぱいお勉強した1日でした\(~o~)/




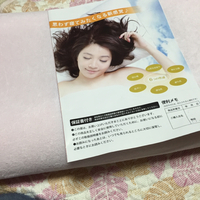











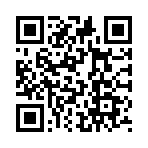

私も知らないことが多すぎて…。
調べるって面倒くさそうで嫌だったんですけど・・・ブログのお陰かな♪
ペットにしたいです(^O^)